「旅行に行かないか?」
付き合いで見始めた映画が案外面白く、夢中になっていたせいで、反応が一瞬遅れた。
「え」
トシキの顔をまじまじと見る。彼はまっすぐにテレビを見ていて、一見すると、映像にのめり込んでいる様子だ。
けれど、本当は違う。身体は正直だ……なんて、大昔に兄が隠していたアダルト漫画の男みたいなことを考える。
トシキの耳や顔は、すぐに真っ赤になるのだ。怒っているときも恥ずかしいときも、私は言葉よりも、顔の赤み加減で彼の機嫌を見抜く。ちなみに、上映中の映画は、興奮するような場面ではない。
こちらを見ようとしない今回は、照れ隠しだと確信する。
さて、どういう風の吹き回しだろう。
私は彼の横顔を観察する。画面はコメディ色全開のシーンなのに、にこりともせずに、きゅっと唇は一文字に引き結ばれている。ストーリーなんて、一ミリも頭に入っていないに違いない。
大学を卒業してから付き合い始めたトシキと私。この二年は、同棲もしている。長い付き合いの中で、旅行に出かけたことは何度もある。日帰りから泊まりがけまで、電車で行けるところも、飛行機に乗る場所も。
でも、そのほとんど……いや、すべて、私から「行ってみたい!」と誘った場所だった。
トシキは完全なるインドア派だ。旅先でも基本的に、娯楽も食事も休息も、宿で完結できるなら、のんびりと過ごしたいというタイプだ。
実際、彼は人混みが嫌いすぎて、フレックス制やリモートワークを取り入れている会社で働いているくらいだ。
私はといえば、旅行に行けば、その土地その土地の名産品や絶景ポイントなど、一通りは押さえておきたい。なんなら、ガイドブックにはまだ載っていない、最新のオススメ店を地元の人に直接尋ねるくらい、ガツガツと楽しみたい人間だ。
真逆のふたりだからこそ、普段の生活は面白くもある。おうち映画だって、トシキが「映画館は面倒だし」と張り切って動画サブスクに課金しなければ、楽しみを知ることはなかった。
自ら外に出るのは、「ゲームのコラボカフェで、限定キャラの配布があるから」など、自分の好きなものに関わるときだけ。
出不精な彼から旅行に誘われるなんて、何か理由があるのでは? と、勘ぐってしまうのは、仕方のないこと。
「行きたくない?」
視線に耐えきれなくなったトシキが、こちらを向く。抱えた膝に、こてんと頭を載せる形で見上げてくる様は、年上のはずなのに甘えたな子犬系男子を相手にしているようで、うっ、と言葉に詰まる。
わかってやっているのか、無意識か。いずれにせよ、性質が悪い。
「っ、行きたい! 行く!」
少々食い気味に返事をすると、彼が一歩引く。こうなると、もはや映画どころの話ではなくなる。
スマートフォンを片手に、「どこ行く? っていうか、いつ行く? シルバーウィークだと、もう予約取れないよね? だとしたら、十月の三連休かな……」と、旅の予定を早くも立てようと勢い込む私を、トシキは手と目で制した。
普段は頼りなく、流されるままに生きていて、ヘラヘラと笑っている。そこがイライラするポイントでもあるのだが、ふと真面目な顔をされると、元々私がアタックして付き合ってもらった経緯もあり、「顔がいい」以外の感想が出てこなくなる。
柔らかな眼差しに、真剣な色を混ぜたトシキは、私の手をぎゅっと握る。些細なスキンシップにときめくような年でもなければ、付き合いたての初々しい関係でもない。でも、ドキドキが止まらなくて、彼の手指の節ひとつひとつまで、敏感に感じ取ってしまいそうだった。
存外大きくて、力が強い。この強引さを、どこに隠していたんだろう。
初めて見る彼の一面に、私は再び恋に落ちてしまいそう。
「旅の予定は、俺に任せてくれないか。いつもアサコにやってもらってばっかりだからさ」
なんかやっぱり、いつもと違う……!
顔の熱さに耐えられずに覆いたくなるが、トシキは私が頷き、全面降伏するまで、手を離してくれなかった。
夏休みはお互いの実家に帰省したくらい。九月の連休に至っては、トシキは仕事を入れたらしい。私もそこは、ゆっくりと家で過ごす予定。
それもこれも、十月の旅行を全力で楽しむためだ。お金はできる限り、節約しておかないと。
彼にすべてを委ねたため、私は口出しをすることはないが、掃除するのに部屋に入ったら、ふせんの貼られたガイドブックが複数冊置いてあった。
行き先は岡山県か。
新幹線で西に行くときに通過したことはあるけれど、ゆっくりと観光したことはない。いつも素通りの土地だ。
岡山といえば、西のフルーツ王国のイメージ。特に桃だけど、シーズンではない。十月だと、ブドウの季節だろうか。フルーツ狩りって、全然元を取れる気はしないんだけど、でもやっぱりワクワクする。
倉敷市の古い白壁の町並みも、普段目にすることのない景観だ。写真映えしそう。
それから国産デニム。工場見学みたいなのもしてみたいし、自分に似合う一本を厳選したい。
瀬戸内海は波も穏やかで、温暖な気候の土地だ。太陽の光を浴びながら、ぼーっと景色を眺めているだけで、都会のストレスが解消できそう。
あと、当然海の幸もはずせない。
「アサコ。楽しそうね」
SNSでハッシュタグ検索をしていると、昼休みが溶けていく。同僚で仲の良いサオリに肩を叩かれるまで、夢中になっていた。持ってきたお弁当は、半分しか食べていない。
慌ててスマホを伏せて置き、昼食を再開する。すでにデザートタイムで、コンビニのアイスカフェオレを片手に隣に座った彼女は、私のスマホを勝手に見た。
「あ、ちょっと」
さすがに一声かけたけれど、別にまずいことをしているわけじゃない。私だって、サオリが食事そっちのけでスマホに夢中になっていたら、気になってしまうだろう。
「岡山? 行くの?」
私が旅好きなのを知っている彼女はそういうと、すぐにスマホを返してくれた。
よくぞ聞いてくれました、とばかりに、私はペラペラと十月の連休について話をする。脳裏に浮かぶのは、トシキの男らしい表情と、握る手の力強さ。
「それでね、彼氏が全部計画してくれるんだって~。楽しみ!」
のろけ全開になった私の話を、サオリは「はいはい」という顔で聞いてくれた。
彼女は既婚者で、なかなかあっちからは旦那さんの自慢話を聞くことはない。
私だって、普段はそんなにトシキのことばかり話すわけじゃないけれど、旅行に誘われたときから、彼への愛が溢れて、誰かに話したくて仕方がない。
サオリは聞き上手だったし、自分からはしないけれど、恋愛トークが好きだ。だから、思う存分、トシキのことをのろけられる。
「あ~、何着てこうかな? 今度買い物行かない?」
「そうねえ……ちょっと改まった服でも持って行くといいんじゃないかな」
思いもよらぬアドバイスに、目を丸くする。 私はサオリとも何度も旅行に行ったことがある。彼氏とは違う楽しみが、女のふたり旅にはある。
旅先ではオシャレもするけれど、なるべく軽装にしているのを彼女は知っているはずだ。歩き回るから、スニーカーで行くし。
意図をはかりかねていると、サオリはにやりと笑った。
「彼氏さん、そんなに気合い入れてるってことはさぁ……ひょっとすると、そういうことなんじゃない?」
「そういうことって?」
考えることを放棄して、間髪入れずに聞き返した私に呆れ返りながらも、サオリは突き放したりしなかった。
優しく肩を抱いて、顔を近づけてくる。内緒話の体勢に、私も背を丸めた。
「プ・ロ・ポ・ー・ズ」
一文字ずつ区切って発せられた単語に、いよいよ私の目は、まん丸になったまま、戻らなくなりそうだった。
「ぷっ」
それ以上先を続けることはできずに、固まる。
プロポーズ。
そりゃ、私もトシキもいい年だし、付き合いも長い。お互いの両親とも顔を合わせていて、関係性も悪くはない。彼の家に年賀状や暑中見舞いなど、季節の挨拶をして、「いい嫁になりますよ」アピールは、同棲する前から続けている。
「今までと違うんでしょう? 絶対そうだって」
「そ、そうかな……」
ガイドブックの存在を思い出す。ふせんの貼られたページまで確認していないけれど、観光名所以外にも、雰囲気のいいレストランの情報なども調べているんじゃないだろうか。ドレスコードのあるフレンチだとか、創作和食の店だとか、とにかくオシャレな店。
「そうかなぁ……!」
求婚経験者であるサオリに肯定されると、そんな気がしてくる。一応、ワンピースとパンプスを用意していこうかな。デニムにスニーカーでは、さすがにそういう店は行けない。
妄想ファッションショーを脳内で繰り広げる私を、サオリは生暖かい目で見守っている。
そんな彼女が、ふと真顔になった。
「まぁでも、旅行は人の本性が露わになるところでもあるからねぇ」
旅の恥はかき捨て、なんて言葉もあることだし。
サオリの忠告はいまさらだった。ふたりきりの旅行は何度も経験しているし、第一、幻滅するなら、これまでの関係の中で露呈している。
笑い飛ばす私に、サオリも「ま、そうだよね」と、肩を竦めた。
「楽しんできてね。報告待ってる」
「うん」
もしも本当に、トシキが私にプロポーズしてくれて結婚となれば、彼女に友人代表のスピーチをお願いしようと思った。
「あ、あとお土産も」
「わかってるよ」
十月に入ってから、毎日私はそわそわしっぱなしだった。
街歩き用は手持ちの服や小物で間に合わせることにして、プロポーズに備えた――とは言えないので、近々ある友人の結婚式用のものだと言って、ワンピースとパンプスを新調した。
ハンガーに吊して、トシキからも見える場所に飾る。私の方は心の準備はできていますよ、という控えめな意思表示のつもりだ。
買ってきて身体に当てて「見てみて!」とやったときには、ゲームの手を一瞬だけ止めて、「似合ってるよ」と言ってくれたドレス。見ているだけ、触れているだけで嬉しくなって、にやにやしてしまう。
しかし、日が経つにつれて、私は焦りを覚えるようになった。
「ねぇ。何時の新幹線に乗るの? 宿泊はホテル? 旅館? 温泉とかある?」
宿泊先によって、荷物は多少変わる。温泉があるのなら、何度も入るだろうから、脱ぎ着しやすいようなカップ付のインナーが便利だし、ホテルの部屋は乾燥するから、対策グッズを持って行きたい。
私の質問に、トシキは気のない返事を寄越した。
「あー、うん」
とだけ。
予約も旅の計画も、全部自分がやると言ったから、信頼して任せていたが、さすがに日にちが迫ってきていた。
「サプライズなんだから、教えるわけないだろ」
しつこく食い下がって聞けば、イラッとしたのを隠さない様子で、彼は私を睨みつけた。手元のスマートフォンからは、ゲームのBGMが流れっぱなしである。
私はちらりと、部屋の隅に置かれたボストンバッグを一瞥する。自分の荷物は最低限詰め込んだものの、トシキは何の用意もしていない。
そういえば、これまでもそうだった。旅行に行こうと私が誘い、トシキが「まぁいいけど」と、軽く返事をする。予約も計画も全部私がひとりで立てて、荷造りですら、当日になっても何も準備していない彼の、替えの下着なんかを突っ込むのだ。
今回も、私がやらなきゃダメ?
将来、結婚して子どもができたときの家族旅行なら、家族の分の荷造りをするのは当然かもしれない。けれど、今はまだ同居している恋人同士。触れられたくないものだってお互いあるんだから、自分ですべきことはしてほしいというのは、わがままだろうか。
「とにかく、家出る時間も決まるから、お願いだから新幹線の時間だけでいいから、教えて。わかった?」
「はいはい」
スマホから目を離さないトシキは生返事で、結局何度催促しても、前日まで時間を知らされることはなかった。
『旅行って、人の本性が露わになるところあるじゃない』
サオリが言っていたことが身にしみたのは、当日になってからのことだった。
何の根拠もなく、恋人が自分のために準備をしてくれる旅行は、楽しくなるに決まっていると思っていた。
当日、朝早くに新宿駅に連れていかれた。新幹線が止まる駅じゃない。
岡山のガイドブックは、なんだったの?
そう尋ねると、少しばつの悪そうな顔をする。
「サイコロ振ってテキトーに決めてたんだけどさ……やっぱ、遠いじゃん?」
むっつりと押し黙った私に、トシキはさらに重ねて、
「山梨も有名じゃん、桃。アサコ、桃好きだろ?」
と言う。
「もうとっくに、旬は終わってるよ」
突き放すと、今度は彼が黙ってしまう。自分を否定されると、すぐに不機嫌になるのは悪い癖だ。
別に、山梨が悪いわけじゃない。東京から近いけど、あまり観光というイメージがないだけ。でもそれは、岡山だって同じなのだ。通過駅でしかなかったのだから。
ただ、どこへ行くのかくらいは、やっぱり事前に教えてもらいたかった。
新宿からは高速バスに乗った。観光会社が出している、バスツアーというやつだ。
「やっぱ、こういうのはさ、自分で考えるよりもプロのコースに乗るのが一番だよな」
ようやく眠気が覚めてきたのもあるかもしれない。トシキは少しだけ、気分がよさそうだった。
私には、後づけの言い訳にしか聞こえない。どうせ、予約したりなんだりが、面倒になっただけなのだ。どれだけお得に旅費を工面するか、頭を悩ませるのも、旅行の醍醐味だというのに。
周りは年配のグループ客ばかりだった。かしましいおばさま方や、せっかくの旅行の日なのに、朝早くから起こされて不機嫌丸出しの旦那さんと、それを宥めようとする奥さん。
私たちを除くと、一番若くても四十代くらいの女性客がふたり。みんな銘々に喋っていて、ガイドの女性の話は、ほとんど耳に入っていない。
トシキもまた、スマートフォンに目を落としていて、お決まりの「右手に見えますのは~……」という観光案内はまるっきり無視だ。私は逆に、彼の顔を見ていたくなくて、車窓に移り変わる景色ばかりを見ている。
山梨もまた、フルーツ王国を打ち出した県だから、やりたいと思っていたブドウ狩りはできた。
天気は曇り空から、やや雨がち。岡山だとばかり思っていたから、西日本の天気予報しか見ていなかった。向こうは晴れマークが続いていたし、気温も高かった。
おかげで、農園でブドウを食べている最中から、寒くて震えていた。薄手の上着一枚じゃ足りなくて、手持ちのストールをしっかり巻いた。
その後もワイナリーやらお昼ご飯はほうとうなどの郷土料理を食べたあと、バスに乗り込む。
あれ? そういえばこういうバスツアーって、ほとんどが日帰りだったよね?
「ねぇ、トシキ」
「うん?」
早朝から行動していたせいで、座席についた瞬間から目を閉じていた彼に話しかけると、鬱陶しそうに返事をされた。
「このあとの予定って、どうなってるの? 泊まりじゃないの?」
二泊三日分の荷物の入った大きめのボストンは足下、前の席の下に押し込んでいる。他のお客さんはみんな、ショルダーやトートバッグなど、最低限の荷物だ。
トシキは半目を開けて、「いや、日帰りだけど?」と、あっさり告げた。
「このあとは土産買って、新宿に帰る。向こうでどっか適当な店入って、そこで飯食おうぜ。話したいこともあるし」
ニヤニヤしているトシキの頬は、わずかに赤かった。
彼の言う「話したいこと」は、サオリの予想通り、プロポーズなのかもしれない。彼は落ち着かない様子で、胸のポケットあたりを触っている。
けれど、私は到底喜べない。
日帰りなら、三連休に合わせて来る必要はなかったじゃない。
イライラする気持ちを抑えて、私は頬杖をついて、それ以上、彼と会話することを拒んだ。
バスに揺られ、おばさま方の尽きることのないおしゃべりをBGMにしながら、私はこれまでのことを思い返す。
今日のことだけじゃない。これまでの旅行のこと、それから日常の生活のこと。隣ですっかり寝息を立てている男への気持ちが、真実のものだったのかすら、よくわからなくなってくる。
旅に出かけるときは、準備から楽しみたい私が、ガイドブックやスマホを持って「どこ行きたい?」と尋ねても、常に「お前の行きたい場所でいい」と言う。
その割に、並んででも食べたいと思って行った店に行けば、「時間がもったいない」と、ファストフード店にふらっと行ってしまう。
「食べたければ、お前は並んだままでいいよ。食い終わったら、先に宿に行ってるから」と言うけれど、それではふたりで旅行に来た意味がない。
結局、私も列を抜け出して、家や会社の近所で食べるのとまったく味の変わらないハンバーガーを咀嚼するはめになる。
別に、高くてよいものが食べたいというわけじゃない。
ラーメン屋だって行くし、地元のおじさんたちが行く、ちょっと薄汚れた大衆居酒屋だって、安くて美味しくて好きだ。
その土地の名物や旬の食材を使った素朴な料理は、旅の大きな目的だ。スケジュールには余裕をもっているし、多少の待ち時間は織り込み済み。他の観光スポットでの見学にも、問題はない。
なのに、彼は絶対に、長時間列に並んでまで食事をすることを、よしとしない。
窓の外の景色が流れていく。東京のビルやマンション群とは違う、一軒家が点在する田舎道。果樹園や野菜畑の色合いで、秋の深まりを知る。
たまたまバスが止まったところに、直売所の案内看板が立っていた。
案内とはいっても、矢印すら書かれていない不親切なもの。「桃」と太く歪んだ手書きの文字は、いつからあるのだろう。
もう、桃なんてとっくに終わっているはずなのに。
夏には、手入れをされているのかもしれない。十月の今となっては、周りには草が生い茂っていて、私しか気づいていないだろう。
色褪せた看板は、打ち捨てられているといっても、過言ではない。
ラブラブな恋人関係を「旬」と表現できるなら、私たちの関係は、とっくに旬が終わってしまっている。
いびきをかいて熟睡している男への愛情は、枯渇している。旅行の話が出たときには、あんなにも楽しみにしていたのに。一瞬で冷めることもあるのだな、と、他人事のように思う。
横目で寝顔を見ながら、今後のことを考える。
蜜月はすでに遠い。いい年の大人だから、多少の妥協――「旬」が過ぎた状態で結婚はするものなのかもしれないと、頭ではわかっている。
それでも、彼と一緒になりたいという気持ちは、すでにない。
この男は、結婚したから、子どもができたからといって、劇的に変わるなんてこと、ありえない。
「ん? お……着いたみたいだな」
到着したのは、道の駅。ここを過ぎたら、高速に乗って東京へさようなら、だ。
あくびをしながら、財布を片手に降りる彼に、「ちょっと先行ってて」と、笑った。
特に何の疑いもなく、トシキはバスから出て行く。他のお客さんが出るのを見送って、私はボストンを引きずり出した。
「あの!」
談笑している乗務員に声をかける。客が残っているとは思っていなかったふたりは、一瞬ぎょっとした顔になるが、さすがはプロ。すぐに笑顔になると、「どうなさいましたか?」と、優しく声をかけてくれる。
「私、ここで降ります! 用事できたんで!」
「は?」
あっけに取られているガイドの女性は、私を遮ることもできない。
「連れにはあとで連絡しておくんで、ご心配なく。っていうか、無理矢理連れてこられただけなんで、あいつと最後まで一緒にいたくないんです」
一気に言い切って、私はダッシュでバスから離れた。勢いで言っておけば、どうにかなるだろう。
道の駅にはタクシー乗り場もあり、私はトシキに見咎められないように、飛び乗った。
白髪頭の運転手さんは、きっとこの道数十年のベテランにちがいない。尋常でない私の様子を見ても慌てず、どころか事情を察してか、すぐに車を発進させてくれた。
ガイドのお姉さんがミラーに映るのを見て、肩の力を抜く。
「お客さん、どこ行きます?」
さて、どこへ行こう。
お仕着せのバスツアーとは違い、もうどこへだって行ける。
山梨のことは何も調べていない。だからこそ私は、呼吸を整えて運転手さんにオーダーする。
「運転手さんのオススメのお店に連れて行ってください!」
(了)


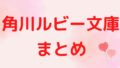

コメント