今日も散々だった。
夜になってもちっとも涼しくならない中、ふぅふぅと息を切らして坂道を上る。デブではないが、年齢のわりにだるんとした身体は、上り坂にすぐにくじけてしまう。
家賃の兼ね合いで選んだ家だが、もっと不動産屋で粘るべきだった。
べき、べき、べき。いつだって、強い義務感や後悔が、頭の中に渦巻いている。
現場を知ろうともしないプロデューサーの、あっちこっちと風に吹かれるがままに意見をコロコロと変える体質。『もっとライトユーザー向けにならないか?』それに苛立ったディレクターによるパワハラ。『言われたとおりの作業しかできねぇんなら、AIの方がマシだろ』報告したバグ一覧を見て、舌打ちをするプログラマー。『このくらい自分でなんとかしろよな。使えねぇやつ』……。
何にもやりたくなかったけれど、スマホのゲームアプリだけはポチポチと続けられた。まともな仕事を探せと、親に家を追い出されたとき、ゲーム会社で働こうと思い立ったのは、それだけが理由だ。
未経験者でもできるのは、実際にプレイしてバグを見つける、デバッガーしかなかった。プログラマーと兼務している人間もいるが、俺にはその技術はない。
イライラすると、タバコの味が恋しくなる。市の条例云々あるが、人通りのない、終電後の夜中だ。関係ない。
ポケットを探ると、潰れた箱が指先にあたる。同時に、カサリという音もした。なんだっけ? と取り出したのは、飴ひとつ。
同じくデバッガーとして参加している、遠山という女からもらったものだった。
「私たち、プログラミングは勉強中ですもんねー。っていうか、勉強する時間よこせ! って思いません?」
嫌味を聞き流して頭を下げ、ようやくデスクに戻ってきた俺に、そっと彼女は囁いた。入社は先輩でも、遠山は年下だった。
はつらつとした笑顔は、オフィス内では異質で、だからこそ彼女は特別扱いされていた。元気に触れてプラスに傾く人間もいれば、逆の人間もいる。俺は後者だ。
気を利かせて雑談をしてくる彼女に、俺は「あぁ……」と曖昧に頷いた。消耗しているときに、彼女の相手をする気力はない。激励の飴はポケットにイン。そのまま忘れていた。
なんとなく、タバコの苦さを求める気持ちは収まって、もらった飴の封を切る。真夏の暑さに、一日中放置されていた飴は溶けてしまっていて、取り出すのに苦労した。
口に放り込んで、すぐに後悔する。特別な子どもにしか与えられないキャンディーは、平凡で平均以下の大人にとっては、素朴すぎてうしろめたい。
タバコの煙は宙に消えるが、吐き捨てた飴は残る。高校を卒業してから数年、俺もいい大人だ。飴を含んだまま、家路をえっちらおっちらと歩く。
自宅にたどり着くまでの間に、飴はすっかり小さくなる。どのタイミングで囓り割るのが正しいのかわからずに、結局最後は、限界まで小さくなったところを飲み込んだ。幼い頃からそうだ。ガラスの破片を嚥下するような不快感。
鍵を開ける。ひとり暮らしの部屋は、当然真っ暗だ。前の住人が残していった、薄汚れたレースカーテンが、ひらひらと動いているのを見て、舌打ちをした。
朝のわずかな時間、電気代の節約のためにエアコンは入れない。窓を開けてどうにかやりすごすのだが、こうやって閉め忘れることがしょっちゅうだった。
電気をつける前に、散らかった部屋を、慣れたステップで渡って、窓を閉める。網戸が緩くなっているせいで、羽虫たちが灯りに集まってきてしまうかもしれないからだ。
エアコンを入れて、電気をつけ、そして「彼」はのんきな声を上げた。
「おかえりぃ」
と。
ムシ男は、物心つく前からの幼なじみだった。
もちろん、本名じゃない。彼のあだ名は、ランドセルの中でオオカマキリの卵を孵化させて、先生も生徒もパニックに陥れたところから名づけられた。
「でも、おれは、虫が好きだからさぁ」
へらへらと笑い、帰り道ではアリの行列を懲りずに追いかけていってしまうムシ男は、俺とは兄弟同然に育った。
休み時間は、おとなしく昆虫図鑑を眺めて、目をキラキラさせているムシ男。俺もまた、虫は嫌いじゃなかったし、外で遊ぶよりもゲームをしたり、本を読む方が好きだったから、教室にいる男子は、俺たちふたりだけだった。
女子は「鬼ごっことか、子どもっぽい」と、誰かの席に集まって、ひそひそとはしゃいでいる。俺たちは、透明人間がひとりとひとり、好き勝手に過ごしていた。
彼が話しかけてくるのは、集団下校でひとりずつ抜けていって、誰もいなくなったときだけ。馬鹿だけど、わきまえている。
彼の隣にしゃがみこんで、お互いに目を合わせない。じっとアリの隊列を観察しつつ、ぼそぼそと喋る。
「俺も、虫は好きだよ。でも、ランドセルで飼うのはなあ」
「だってさぁ」
俺とムシ男は、一緒の家に帰る。
「ただいま」
と、挨拶するのは俺ひとりだ。ムシ男は、さっきまで饒舌に語っていたくせに、家に入ると途端におとなしくなる。
「おかえり」
手を洗って、母親からおやつをもらう。一個しかないドーナツを、俺は半分にして、ムシ男にやった。彼は俺と同じタイミングで食べる。
夕飯もひとり分しか出てこない。両親はムシ男のことを預かっているくせに、無関心を通り越して、見ていないのだ。
何度か抗議しようと思ったけれど、その度にムシ男が俺の肩を掴んで止めた。
「大丈夫だよぉ」
その笑顔に毒気を抜かれ、怒りはどこかへ消えていく。
同じ家で育ってきたムシ男は、そして当然のように、ひとり暮らしを始めた俺のところに、姿を現すようになったのだった。
スケジュールがだいぶ遅れているのは、誰のせいなんだろう。このままではリリースを予告した日に、配信が間に合わない。
ディレクターはいつもに増して機嫌が悪く近寄りがたかったし、彼にもっともきつく当たられるプログラマーたちも、戦々恐々としていた。
ゲーム制作はチーム戦だと言うけれど、ボロボロとこぼれ落ちていく人間が多いのも頷けた。
残業代は、一日一時間までしか出さないと言われていた。契約書にはなく、口頭での念押しだったが、頷いた以上は、遵守する必要があった。たとえそれが法令違反であったとしても、直接金をくれるのは会社だ。
きっかり一時間でタイムカードを押して、席に戻る。ここからが本当の仕事の時間といっても、過言ではなかった。他の社員もほとんどが残っていた。
「バグって、多少あった方が面白くないですか?」
デバッガーには、細切れになったデータが送られてくる。見かけによらず、根っからのゲーマーである遠山は、それが不満であると鼻を鳴らした。
先行プレイできると思ったから、応募したのに、と。
聞き流していると、「聞いてます?」と、追撃してくる。まさか俺に話しかけているとは思わなかった。
ちらりと目を向けると、嬉しそうだ。
「ドラクエⅡに、はかぶさの剣ってあるじゃないですか」
この会社の人間のほとんどが、発売当時は産まれていない。
「世代じゃないだろ」
なんで知っているんだ、と呆れると、「常識ですよぉ」と言う。俺だって、実況動画でしか知らない。
「はかいのつるぎとはやぶさの剣、だっけ?」
えげつない攻撃力と引き換えに呪われた「はかいのつるぎ」と、攻撃力は低いけれど二回攻撃ができる「はやぶさの剣」、両方の長所だけを活かすため、バグを利用した秘技が、「はかぶさ」だった。
「知ってるんじゃないですか」
と、楽しそうな彼女の指は、しかし、恐ろしい速さで動いている。
「そうです。あのバグ技がなければ、タイムアタックも伸びないし、低レベルクリアなんてもってのほかなんですよ? そう考えると、バグって面白いっていうか、むしろ必要不可欠なんじゃないですか?」
俺は無言で、端末に向かった。それが答えである。
たまたま「はかぶさ」はプレイヤーに恩恵があっただけ。しかも、ドラクエⅡの発表時とは、時代が違う。
普通、バグはプレイに致命的な影響を与える。だから消さなければならないのだ。
無反応になった俺に、空気の読める彼女は、肩を竦めてそれ以上話しかけてこなかった。
そして、ひとり、またひとりと消えていき、遠山も、「私も先に帰りますね。戸締まりよろしくお願いします」と、礼儀正しく頭を下げて出て行った。
「下手の横好きだよねぇ」
いつの間にか会社にまでやってきたムシ男は、集中して操作をしている俺の隣に腰を下ろしていた。
「うるせぇ」
デバッガーに求められるのは、ゲーム好きということよりも、根気強さ。それから、エンジニアと円滑にやりとりするためのコミュニケーション能力だった。
前者はどうにかなっているが、後者が致命的に足りないのはわかっていた。
そのため、報告書には口頭でいいような些細なことまですべて、並べ立てる必要があり、作業の遅れの原因になっていた。
昼に買っておいた栄養クッキーを、ぶつぶつと会社やゲームへの文句を唱えつつ、貪る。
ムシ男は俺のチェックしているゲーム画面を見つめながら、同じように貪り食っていた。
ムシ男とはいつだって、食事を分かち合ってきた。家のおやつや食事、給食すら彼には配膳されない。
極めつけに、小五のキャンプのときは、どこの班にも入れてもらえなかった。
慣れない野外活動と、昼のおにぎりを食べすぎて体調を崩した俺が、ようやく動けるようになったときには、夕飯のカレーを準備する時間だった。
俺は、ムシ男とふたり、先生のつくったカレーを、隅の方で食べた。大盛りにして、と言ったら、「さっき倒れたばかりなのに」と、怪訝な顔をされた。そうしないと、ムシ男の分は用意されないから、仕方ないのだ。
ムシ男は無言だった。誰かの気配があると、彼はそのお喋りを封印して、頑なに口を閉ざす。
今、会社には俺とムシ男しかいない。
「ふたりだと、おいしいねえ」
ドラッグストアの激安PB製品は、パサパサの食感だったが、ムシ男が楽しそうなので、俺も頷いて、コーラで流し込んだ。
「おい。なに寝てんだ。いいご身分だな」
怒鳴り声とともに、こつんと頭に軽い衝撃を受けた。文字通り叩き起こされて、気分は最悪だった。
栄養クッキーを食べてから、仮眠を取ろうとタイマーをセットして、うとうとしていた。それが本格的な睡眠になってしまったらしく、ゲームのプレイ画面は固まっていた。
慌てて弄ろうとすると、「余計なことすんな!」と、プログラマーに激高されて、俺は首を縮めた。そのまま席をどかされて、かといってどこへ行けるわけでもなく、俺は作業をする後ろで、そわそわとするばかりだった。
「あの、ありがとうございます……すいませんでした」
か細い謝罪と礼を、プログラマーは受け取らなかった。鼻息も荒く、自分のデスクへと戻っていく。
それから再び、ディレクターからの叱責を、立ったまま受ける羽目になった。トイレに行きたいと思っても、ひと段落するまでは我慢しなければならなかった。丸めたファイルで、俯いた後頭部を何度も叩かれるのを、惨めな気持ちで受け入れていた。
楽しいゲームの裏側では、ブラックな体制ができあがっている。
そうしている間も、隣にはムシ男がいた。相変わらず笑っている。
俺がひどい目に遭っているのが、そんなに嬉しいのかよ。友達甲斐のない奴め。
ようやく解放されて、慌ててトイレに行く。
「おい、ムシ男。お前、ああいうときはちょっとは庇えよな」
手を洗いながら、鏡越しに言う。ムシ男は表情ひとつ変えない。だんだん腹が立ってきて、俺は拭いていない手をパッと払って、水滴を奴に飛ばしてやった。
「つーか、いい加減帰れよ」
今までは、家にしか来なかったのに、急に職場にまでついてきて、隣で一緒に画面を見つめている。
「ええ~」
間延びした声は、小学校の頃から変わらず、のんきなものだ。深く溜息をついた俺に、「あ、おはようございます!」と、遠山が声をかけてきた。ちろちろと、俺の姿を頭から爪先まで観察してくる。
「結局昨日、泊まったんですか?」
隣に並んで歩き始めた彼女との距離の測り方が、いまいちよくわからなかった。シャワーを浴びていないから、臭いかもしれない。一歩離れて、様子を見る。
「ああ、まぁ」
適当に相づちをうつ。ふと逆隣を見れば、ムシ男はいつの間にか、姿を消していた。唯一苦手な、黒光りする例の虫並の素早さだった。
そういえば、ムシ男は男よりも、女子に嫌われていたっけ。女の大部分は、昆虫のよさを理解しない。担任も女だったから、ムシ男を気持ち悪がる女子の味方だった。
だから俺も、女が苦手なのかもしれない。遠山は、デスマーチ一歩手前の状態でも、きれいに着飾って化粧もしてくる、いわゆる「女らしい」女だった。真正面からなかなか対話するのが難しい。
「うちのゲーム、どうなっちゃうんでしょうね?」
「と、いうと?」
目を合わせずに、問い返す。
今、俺たちが必死になって作っているのは、「イマジナリーフレンド」というゲームアプリだ。
読んで字のごとく、「架空の友達」が、主人公と成り代わろうとして襲いかかってくる、ホラー要素のあるリズムゲームだ。
プレイヤーキャラは可愛い女の子を取り揃えていて、彼女たちがなぜ、「イマジナリーフレンド」を生み出すに至ったのか、過去の真実や深層心理に迫っていく。
「プロデューサーが、敵も萌えキャラにしろとか言い出したって」
イマジナリーフレンドとして友好的なときは、シルエットで登場するが、敵対心むき出しで襲いかかってくるときには、わかりやすいクリーチャーの姿を取る。デザイナーやグラフィッカーが、張り切っておどろおどろしいキャラを作り上げていた。
「――さんは、どっちがいいと思います?」
萌えキャラとクリーチャー、どちらのゲームの方がプレイしたいか。そんなの決まってる。
「モンスターらしい方」
「へー。意外ですね」
小太りの俺を、典型的な萌え豚とでも思っているのだろう。恥ずかしくて、自然と早口になる。
「イマジナリーフレンドって、脳のバグみたいなもんだろ? なら、消さなくちゃいけない」
「あー。デバッガーらしい発想ですね。バグ、即、断! って感じで」
きゃらきゃらと、「うまいこと言った!」みたいに笑う遠山に、少しムッときた。
だって、罪悪感のわかないビジュアルの方が、やりやすいじゃないか。
そう言うと、俺は不意に鋭い視線を感じた。
ムシ男だった。
少し離れたところから、俺を見つめている。
クラス中から無視されたり、ムシ男と呼ばれて陰口をたたかれているときですら、見たことのない彼の顔に、俺は立ち尽くした。
ムシ男はずっと、情けない笑顔を浮かべていた。笑うと目がなくなって、眉もハの字になる。
今の彼は、泣いているとも、怒っているともとれる無表情だった。
「どうしました?」
遠山は、首を傾げた。
その奥にムシ男はいたが、俺が彼女に目をやった次の瞬間には、いなくなっていた。
「バグって虫のことなんでしょう?」
夜、オフィスにひとりになると、ムシ男が現れる。午前中のあの顔が嘘だったみたいに、へらへらと笑っている。
「そうだ」
目が霞み、眉間を揉むが、気休め程度にしかならない。眼鏡の度も合わなくなってきていて、次の休みには眼鏡屋で新調しようと決めた。眼科も行きたいから、一日がかりだ。いつになるだろう。
正しい操作をする。動く。間違った操作をする。動かなくなる。ついうっかり、ミスタップすることは誰だってある。そのせいで画面がフリーズしたり、アプリが落ちたりするのを、事前に確認するのがデバッガーの業務だ。
どんな操作をしたのか、そして画面がどうなったのかを報告書にする。プログラマーが原因を究明して、直す。
その作業を、何千回、何万回と繰り返して、ようやく一本のゲームタイトルがリリースされるのだ。
メモを取りながらのプレイに、ムシ男は不満げだ。
「虫を消すの?」
「当たり前だろ。そうじゃなきゃ、配信できない」
バグが多すぎたり、クレーム対応が悪ければ、誰も有料ガシャを回してくれない。ゲームアプリは基本無料だが、慈善事業じゃない。
ゲームは人生だ、みたいなことを言っていたのは誰だっけ?
どっかの有名ゲーマーだったか。
人生がゲームなら、バグはそれをめちゃくちゃにする、悪だ。見つけたらやっぱり、徹底的に叩くべきだ。
「じゃあ、おれのことも消す?」
何をわけのわからんことを。
怒りにまかせて顔を上げた俺の目に映るのは、虚空だった。確かに隣にいたはずなのに。
え、と思うと同時に、今度はまた、別の方向からムシ男の声が聞こえる。
「おれは、君の人生のバグみたいなものだよ?」
こんなにはっきりと喋る彼のことを、俺は知らない。誰だ。
また別のところに彼は出現する。声の瞬間後に振り向いても、遅い。そのときにはもう、ムシ男は消えている。
あれ、ムシ男って、どんな顔してたっけ?
「ほら、どんどん消えてきた」
心を見透かして、彼は笑う。
「ムシ男?」
「それでは、問題です」
チャーラン! と、効果音も口頭でつける。
「ムシ男と呼ばれていた男の子の、本名はなんでしょーか?」
「はぁ?」
そんなの簡単だ。俺とこいつは、ずっと兄弟みたいに育ってきた。
チッチッチッ……ムシ男の唇が、時を刻む。
答えが出てこない。そんな馬鹿なこと、あるか。俺はこいつの唯一の友達で、こいつだって俺にとっては、唯一の。
「ブッブー。時間切れです」
無慈悲に告げたムシ男は、正解を述べる。優しく愛の籠った目を、青ざめた俺に向ける。
「ムシ男の本当の名前は……潮。潮淳也」
ちがう。
それは、俺の名前だ。
「おれは君が本当にやりたいことをやってきたよ。アリの観察も、ひとりで図鑑を見ながら笑うことも。おれと一緒だったから、できたでしょう?」
ああ、そうだ。カマキリの幼虫を鞄から溢れさせて、「潮じゃなくて、お前なんかムシ男」だと、クラスから嫌がられていたのは。
「バグは人生にいらないっていうのが君の価値観なら、おれはもう、お役御免だね」
待ってくれ。どこへ行くんだ。
手を伸ばす、届かない。名前を呼びたくても、声が出ない。
ムシ男は、にこやかに笑った。やっぱり眉は、困り眉だった。
「大丈夫。全部おれが引き受けるよ。なにせ俺は、ムシ男だからね。じゃあね、大好きだよ。君がおれを忘れても……」
「ま……」
ようやく発した声と同時に、バチン、と頭の中で音がした。銅線がショートして、焼き切れるような火花。痛みとともに、昏倒する。
「うそ! 潮さん!? どうしたの!?」
帰ったはずの遠山の声を聞き、俺の意識はブラックアウトした。
突然、意識不明に陥った夜、遠山は差し入れを持ってきてくれたのだった。連日の残業で、絶対に栄養クッキーしか食べてないと思ってたから、と。
彼女が来てくれなかったら、俺は朝まで床に寝ころんだままで、出勤してきたディレクターに、蹴とばされていただろう。
救急車で運ばれた俺には、記憶の混乱が認められ、しばらく入院することになった。
世話をしに来た親や、見舞いに来た遠山に、俺はこれまでの人生をわーっと語った。
虫を愛でていたら、ムシ男と呼ばれるようになったこと。受けてきた無視や言葉の暴力。無気力なニートになってしまったこと。今はブラック企業で、バイトなのに正社員並みの残業をしているということ。
泣いたり、かと思えば急に笑い出したり、せわしない感情の乱れを、彼らは黙って受け止めてくれた。
「無理に追いだして、悪かった」
父は、しばらくゆっくりしろと、固い顔で言った。母は泣いていたし、遠山は、
「辞めちゃいましょう! でもタダではやめない! 一緒に労基いきましょうね!」
と、拳を握った。
俺の人生はバグばかりで、王道ストーリーのようにはいかない。
けれど、一緒に日々を戦おうとしてくれる人がいることに、あらためて感謝をする。
本当はもうひとり、誰か大切な、大好きな仲間がいたような気がするのだが……。
ともかくこれからも俺は、俺自身を生きていこうと思う。
体調を戻すのと同時に、ゲーム制作に必要なスキルを学んだ。俺はやっぱり、散々なパワハラを受けても、ゲームが好きらしい。適当な理由をつけて選んだ業界だったが、思いのほか気に入っていたことに、今更気づいた。
「遠山が前に言っていたこと、今ならわかるような気がする」
最低限のプログラミング技術を身につけたところで、遠山が誘ってくれて、彼女と同じ会社に勤務することが決まった。隣でキーボードをリズミカルに叩く彼女に、俺はそう話しかけた。
「どれのことですか?」
まさか忘れているのか、と驚いて彼女の顔をしげしげと眺める。
「私ってお喋りだし、潮さんが聞き上手だから、ついいろんな話をしちゃってですね」
彼女の言い分に声をあげて笑い、俺は告げた。
「ゲームには、多少のバグがあった方が、面白いってこと」
そしてそれはおそらく、人生もそうなのだろう。今なら、そう思えた。
だから。
だから、帰ってこい。
誰かわからない、なのにかけがえのないと感じる仲間に、俺は心の中で呼びかける。
『まったく、忘れられないなんて。君は本当に、おれのことが好きなんだなあ』
誰かさんの、へらへらした笑い声が聞こえたような気がした。
(了)

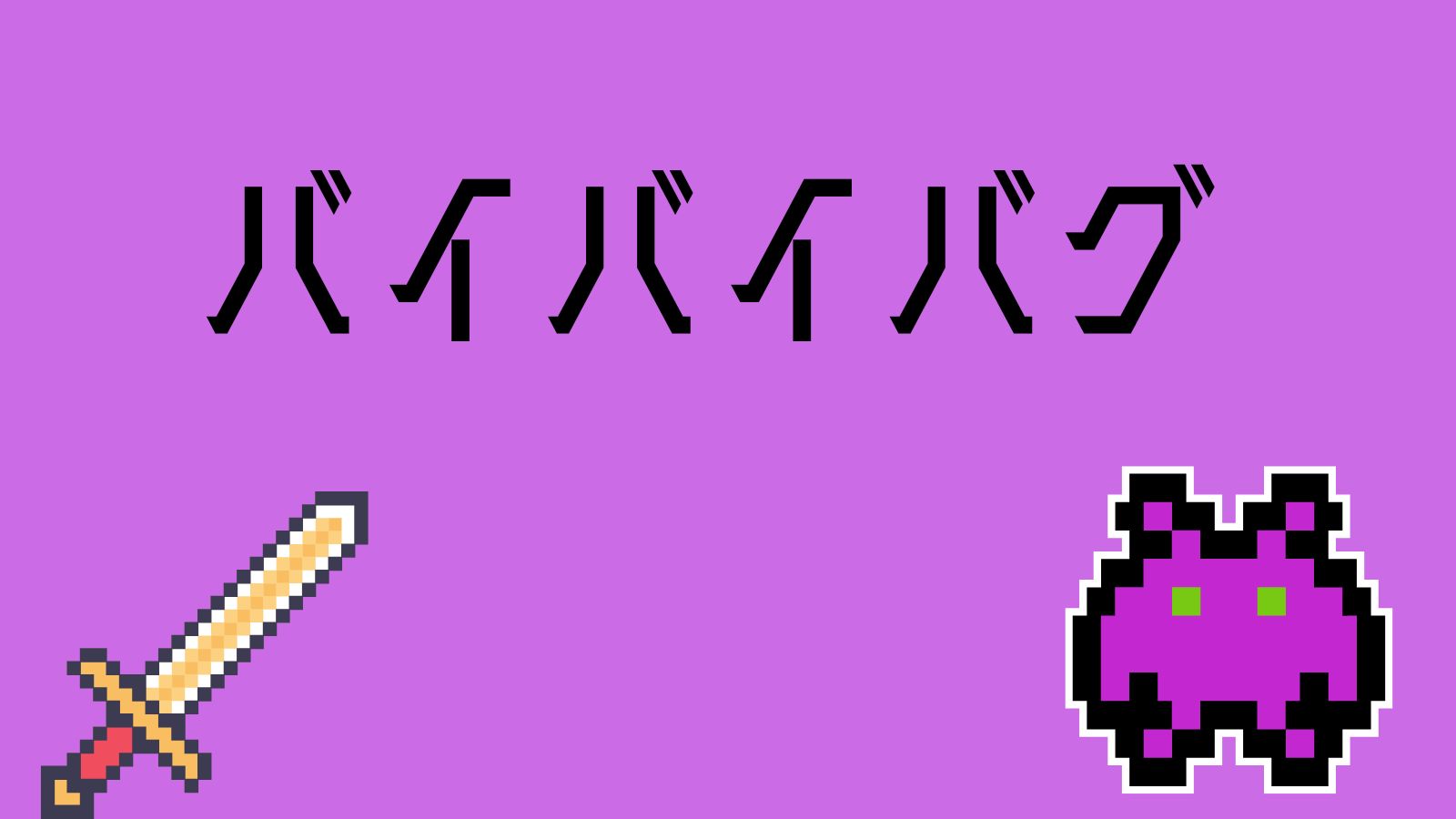


コメント