産みの親と育ての親が違うのは、まれによくある。
積極的には言わないけれど、親密になるにつれて、打ち明け話をするようになる。一般家庭の子には同情され、腫れ物扱いされる場合もあるけれど、「実は……」と、お互いの秘密を共有する友人もいた。
人それぞれ事情はあるだろうが、私の場合は、単純に実母の育児放棄だった。なんて、社会人、医師としての第一歩を踏み出した今だからこそ、軽く言えることなのだけれど。
実母は看護師だったらしい。これは彼女の姉で、私を引き取ってくれた育ての母が教えてくれた。実母と暮らしていたのは物心つく前で、私の記憶に微かに残るのは、丸い背中に、無造作に括った長い髪が垂れ下がっている姿だけだ。
今日もあちこち呼び出されて座る暇もなかった日勤を終え、帰宅する。
「ただいま」
ああ、お腹が空いた。いつもなら、私が帰る時間に食事を用意してくれているのだが、今日は空腹を刺激する匂いが台所からしなかった。
「お母さん?」
台所は薄暗い。亡くなった夫の遺産で裕福に暮らす未亡人。人前では明るく華やかな母は、ダイニングの椅子に座ったまま、ぼんやりしている。
「お母さん!」
もう一度声をかけると、彼女はようやくのろのろと振り返り、初めて私の帰宅に気がついた。
母の前には、一枚の名刺が置かれていた。
「うーん」
細かい作業は、正直得意ではなかった。医者といえば切って縫っての外科医が花形で、母もそうなるように期待しているようだが、私には向いていない。かといって内科もあまり気乗りしなかった。
臨床病棟は忙しすぎて、目が回る。それに比べて、この部屋のなんと穏やかなこと。それも運ばれてくる「患者」いや、「ご遺体」が来るまでの、つかの間の静寂であったが。
「どうしたの、如月。こんなところで」
のっそりと歩く、眼鏡をかけたクマ。法医学者のタマゴは、長い前髪の奥の目を怪訝そうにすがめた。
同期の上坂は、大きなあくびをして、冷蔵庫の中からプリンを取り出した。三連になったカップを、丸飲みする勢いで平らげていく。
法医学研究室には、先輩たちも実験のために立ち寄る。機材は許可があれば、私でも扱える。拾った髪の毛と抜いた自分の髪の毛根からDNAを検出し、鑑定する。
サンプルは、私と育ての母のものだ。
「上坂さぁ」
そこで私は口を噤んだ。上坂には、すでに私の家庭の事情――私がこれまで知っていたすべてのことを、話してあった。彼もまた、血の繋がった家庭という者への帰属意識が低い者だった。
「うん」
相づちを打ったきり、彼は私の話の続きを待っている。律儀なことに二個目のプリンを食べる手を止めて。
「なんでもない」
首を横に振る。同期の中では、一番心を許している相手であっても、さすがにこの話はできない。
あの日、母の前に置かれていた名刺は、テレビ局のプロデューサーのものだった。
母の説明は要領を得ず、昨日、もう一度その人に来てもらった。
佐藤と名乗ったプロデューサーは、三十代後半といったところか。冷房の効いた部屋の中でも汗が止まらない様子で、ハンカチで何度も額を拭いた。
佐藤はひとりではなかった。隣でにこにこしているのは、女性だ。佐藤と同じくらいの年に見える彼女は、客観的には美人なのだろうが、私は手放しに、「おきれいですね」と褒めることはできない。
似ていた。私に。いや、私が、彼女に似ているんだろう。
青海マリエという元アイドルを、私は知らなかった。おそらく、同級生もあまり知らないだろう。芸能人に興味をもったときには、とっくに落ち目になっていた。
「あなたが……」と、芝居がかった涙を見て、私が私でいられた土台になるものがすべて、崩れ落ちていくのを感じた。
マリエの実年齢は、第一印象よりも十歳以上は上だ。そう知った途端に、目元の小じわが気になった。
この人も、私の母であるらしい。
当時は人気のあるアイドルで、恋人の存在は極秘だった。
『でも、若いうちに子ども、娘が欲しかったのよね。ほら、大きくなったときに姉妹に間違われる美人親子なんて、夢があるでしょう?』
自分が狂っているとはちっとも思っていない顔での告白に、眩暈がしたのはどうやら、私たちサイドだけらしい。佐藤は少し困ったように笑うだけだ。
スキャンダルはご法度だし、妊娠出産で体型が崩れるのも嫌。
だからって、代理出産に手を出すなんて。
法改正によって、日本でも不妊治療の一環として認可されたのは、一昨年の話だ。
動機が倫理的におかしいから、現在であってもまともな産科医は手を出さない案件だ。
思わず、今の母を見た。彼女は青白い顔のまま、首を横に振る。知らなかったのだ。妹が、金で自分の子宮を、人生を売ったことを。私を姪だと信じて育ててきたのだ。
『代理出産も合法化したし、もう時効でしょう。それでね、母と子の感動の再会を、この番組で……』
『は?』
時効だって? ふざけるな。
立ち上がり、首根っこを捕らえて追い出そうとした私を、隣に座る母は、全力で止めた。 見上げ、首を横に振る彼女の目は哀れだった。佐藤の隣で「大人になったから、迎えに来たのよ」と、涙を拭き拭きしているマリエよりもよほど、泣きたい気持ちだろうに。
私は母の顔を立て、無言で席に着いた。佐藤は私の剣幕に、今日のところは引き下がることにした。
彼に連れられて帰る間際、マリエは振り向いた。目が輝いているのは、涙のせいではない。
『清香ちゃん、私に似て美人でよかったわぁ。一緒にテレビ、出ましょうね』
中年女性なのに、両のこぶしをぎゅっと握って力説する仕草は、女子高生だった。いや、高校生でもこんなことしない。ぞっとして目を逸らすと、彼女は私の感情をどう受け取ったのか、にっこり微笑んで、手を振って家から出て行った。
さて、私は一週間以内に、佐藤に返事をしなければならない。
会いたい人を探し出し、再会させる余計なお世話の特番の予定は、変えられない。マリエの出演も、目玉として用意されている。代理母という点をぼかして、再現ドラマも撮影中だという。
私が決めなければならないのは、生放送に娘として出演するかどうか。できないのならば、それらしい手紙を用意しろ、とのこと。
どちらも吐き気がする。
昨日のことを思い出して、視線を手元に落としたままのところに、ずい、とプリンがフレームインした。
顔を上げると、無表情ながら目に心配の色を覗かせた上坂が、「とりあえず、元気出しなよ」と、勧めてくる。
食欲はあまりないが、ありがたく受け取って蓋を開ける。スプーンが、彼の使っていた一本しかないことに気がついたのは、それからだった。
青海マリエが病院に現れたのは、夜勤を終えた翌朝のことだった。急患がひっきりなしに運ばれてきたせいで、ほとんど仮眠も取れていない。
髪はボサボサ、顔はすっぴん。どうせ帰るだけだし。小腹が空いたけど、何か買って帰ろうか。
そこに、「あ、清香ちゃーん!」と、脳天気な声をかけられたときのメンタルは、筆舌に尽くしがたい。
「何かご用ですか」
事務的な応答にも、マリエはめげない。両手を握って顎の下に持っていく、ぶりっこポーズは年甲斐もなく、痛い。
一緒にいるのを見られたくなくて、私はそそくさと、彼女を連れてタクシー乗り場に行った。
この間家に来たとき、そういえば彼女の名刺ももらっていたな。事務所の住所がわかるはず。
事務所名を言えばいいだけだったのに、頭はやっぱりまともに動いていなかった。
もたもたと名刺入れを探しているうちに、マリエは勝手に行き先を告げた。
「ちょっと」
と、言いかけて、やめた。文句を言う/言われることによって始まる会話の方が億劫だ。
おとなしく、隣で脚を閉じて座る。揺れる車内、ノースリーブのサマーニットから覗く細すぎる二の腕に、一ミリたりとも触れたくなかった。
マリエが連れてきたのは、彼女の行きつけのレストランだった。営業開始時間まで、まだ少し早いのに、従業員は心得たように、彼女を個室へと案内した。
向かい合って座る。前回は佐藤や母と一緒だったから、まじまじと彼女の顔を見る暇はなかった。
見れば見るほど、自分の二十年後の姿がそこにあるようで、恐ろしい。これまでの人生で、彼女とは一切関わりがなかったのに、遺伝子の影響力の凄まじさにおののく。医学を学んでいても、実地で体感することは、ほとんどないものだ。
勝手に注文された料理に、私は口をつける気になれない。私はこれから帰って寝るのだ。油脂とクリームを多用したフレンチは、胃が重くて眠れなくなる。
マリエは優雅そうな手つきで、ナイフとフォークを使う。「優雅な」ではないのは、どこかぎこちないからだ。白身魚にかかっていたソースが跳ねて、彼女の服を汚す。
「ねえ、この間はちゃんと話ができなかったけど、お医者さんなんでしょ?」
咀嚼中の食べ物が見えるのも気にせず、マリエは喋り続ける。眉をひそめつつ、私は頷いた。差し向かいで人の話を無視できるほど、私は図太くない。
マリエはきゃっきゃとはしゃいだ。
「さすが、私の娘だわ。ね、一緒に芸能活動しましょうよ。美人女医なんて言ってテレビに出てる人、みんなおばさんだもん、清香ちゃん、すぐ人気者よ」
二十代の医者はみんな、研修期間だったり、正式な医師としてはまだ駆け出しで忙しい。コメンテーターなんて、余裕のある人しかやれない。
芸能の世界しか知らないマリエは、世間を知らない。私が呆れてものも言えないのをいいことに、べらべらと好き放題に夢物語を喋っている。
「でもちょっと名前が地味なのよね。なんで清香なんて地味な名前をつけたのかしら。私だったら、そうね、ジュリアちゃんとかキャサリンちゃんとか……」
げっ。
おぼろげな記憶の中で、実母だと思っていた人(実際産み落としたのは彼女だから、実母で間違いないのだが)との生活は、裕福ではなかった。おそらく、養育費は払われていなかったのではないか。
もしもマリエの元に戻されていたとしたら、彼女好みのキラキラネームをつけられ、それはそれで幸福とは言いがたい子ども時代を送ることになっていたのだろう。そうならなかったことだけ、私は実母に感謝した。
そしてふと思った。彼女は闇医療に手を出してでも、愛する男との間に子どもが欲しかったはずだ。なのに、その結果である私のことを引き取らなかったのは、なぜか。
「どうして産ませっぱなしで、私のことを引き取らなかったんですか」
質問というよりは、詰問、いや、叱責に近い緊張した声色に、マリエは気づかない。今はさておき、昔は俳優のまねごともしていたはずだが、空気を読む力はまるで備わらなかったらしい。
食後のデザートをつつきながら、彼女は悪びれもしない。
「だって私、子育てなんてできないもん。バレたら大変だし」
コーヒーしか飲んでいない私の前の皿を引き寄せて、「おいしっ」と微笑むマリエは、化け物だった。
「若いお母さんってステキでしょ? ほら、私たち、本当に姉妹みたい……」
画角を調整して、スマホでツーショット写真を自撮りする。引きつる私の顔に、彼女は最後まで気づかなかった。
胸くそ悪いものを抱えたまま帰宅した私を、母は「何してたのっ」と、出迎えた。おかえり、より先に問いただされて、苛立ちと眠気に支配された私は、マリエのことを隠すのをうっかり忘れた。
母はみるみるうちに萎み、背中を丸めた。先ほどまで目に滲ませていた憤りは消え失せ、次に浮かんだのは卑屈な暗い輝きだった。
この人は昔から、こういう顔をすることがある。
私を引き取ると決めたとき、彼女の夫は存命だった。お互いに少しずつ原因があっての不妊で、子のいない人生を選んでいたふたりのもとに、振って湧いた私という存在。
養父は私によくしてくれた。この先、マリエが過去に熱烈に愛した男が「父です」と名乗り出ようとも、さすがに容認できない。
覚悟と愛情をもって私を迎え入れた彼に対して、母はいつだって、下手に出た。
妹がごめんなさい。あなたとは血の繋がらない娘を育てさせてごめんなさい。余計なお金を使わせてごめんなさい……。
養父はそんな母に、「俺もこの子が可愛いんだ」と言って聞かせたが、彼女は変わらない。次第に諦めて、何も言わなくなった。
私が医大に合格したときも、母はそうだった。手放しで喜んでくれているのかと思いきや、私ではない何かを見つめている、そんな気がしていた。
『やったわね、清香。これでようやく、報われるわ』
これまでの養父母との生活は、幸福なものだった。母のこの言葉は、その事実をなかったことにするようなものだった。
実母に捨てられたかわいそうな娘を引き取った私、苦労して育てた娘が医者になる、ようやく報われる私。
そんな自意識が透けて見える。
「そう……あの人、年の割には若くて美人だものね。一緒に歩いていたら、注目の的ね」
マリエに、勝手に彼女と食事をした私に怒るのではなく、「私は地味なおばさんだから、一緒だと恥ずかしいわよね」という態度に、次第に嫌気がさしてくる。
「ねぇ、お母さん」
母と呼びかけると、彼女は少しだけ嬉しそうに、口元を緩めた。
「私は、どうすればいいと思う?」
マリエと一緒にテレビ出演をするべきかどうか。期限はもうあと数日しか残っていない。 ふっ、とか細い溜息とともにもたらされる答えは、「好きになさい。あなたの人生だもの」という、物わかりのいい模範解答だった。
けれど、彼女の目はまったく別の感情を訴えかけてくる。
ここまで育ててあげたんだもの、私を選んでくれるわよね? あれだけの大金を積んで、医者にしてあげたのよ。まさかここに来て、裏切ったりしないわよね……。
「そう、だね。もうちょっと考えてみるわ」
言いながら、自室に向かった。ひとりきりの部屋は静かで、外で鳴く蝉の声だけが聞こえる。夏休みに入った子どもたちの歓声は一切せず、暑くて家に引きこもっているのだろう。
私が小学生の頃は、違った。ラジオ体操は皆勤賞を狙っていたし、学校のプールが開放されていれば、通い詰めた。海にも山にも行き、泊まりがけの旅行もした。
けれどその思い出の中に、母の姿はひどく希薄だった。夏休み中の母で覚えているのは、塾の夏期講習に勝手に申し込み、私を追い立てる顔だ。
ほら、早く行きなさい。あなたは賢いんだから、勉強していい大学に行って、見返してやるの。
誰を?
生まれ育ちを他人に面と向かって馬鹿にされたことはない。母はとにかく、体面を気にした。
今思えば、それは彼女の妹、私の産みの母をぎゃふんと言わせたかったのだろう。
看護師より上の立場になった娘を、おおいに誇ってくれたのは、これまでの私の頑張りを評価してくれたんじゃない。
自分が、妹より上だということが、私を介して証明できたのを、喜んでいたのだ。
ベッドに寝転んで、マリエと今の母のこと、それから顔すら覚えていない実母のことを考える。
なんだ、そうか。彼女たちはみんな、似たもの同士なのだ。みんな、私のことなんて本当は興味がない。母とは到底言えない人たち。
金、美貌の母娘、ステイタス。愛などそこには、一ミリもない。
なのに彼女たちのうちの誰を真の母とするのか選ばなければならないのは、どんな罰ゲームなのか。
DNA鑑定の結果が出た。当然、今の母との血縁関係は99.9パーセントない。
深夜になにげなくテレビをつけたら、マリエがバラエティ番組に見ていた。私の前での振る舞いは、演技ではなく、素であるらしい。SNSの実況を見れば、「痛いおばさん」と草が生えまくっていた。絶対ああはならないと誓った。
「如月。やっぱりなんか、悩んでる?」
のそのそと歩き回る上坂の身体からは、ほんのりと死臭がした。
病院というのは日常で最も死と接近する場所だ。それでも、ご遺体の解剖を行ったあとの上坂には、近寄りがたいものがあった。
私の表情を見て、彼は心得たように距離を取った。引き出しの中から板チョコを取り出して、「いる?」と言う。首を横に振った。
「ねえ」
「なに」
「最悪の選択肢の中からひとつ選ばなきゃならないときって、何を基準に選んだらいいと思う?」
DNAはマリエ、ともにいた期間は今の母。腹を痛めて実際に産み落としたのは実母。どれも決定的な理由だからこそ、決め手に欠ける。
真剣な顔の上坂に、「軽い気持ちで聞いただけだから」と言いかけたところで、彼は首を傾げた。
「それって、選ばなきゃだめなものなの?」
試験にだって、「あてはまるものがなければ『0』を選択せよ」という引っかけ問題が存在する。
上坂は持っていたチョコレート三枚を、ぬっと私の前に差し出した。ミルクとホワイトとストロベリー。
「俺はどれかひとつ選べないから、全部少しずつ食べる。如月は、今は気分じゃないから何も選ばない」
人生って、そんなもんじゃないのか。
言われて、私の頭からは霧が晴れた気がした。礼を言って、慌ただしく研究室を出る。スマホで呼び出したのは、佐藤の番号だった。
「佐藤さん? 如月ですけど……ええ。そうです。それで、いくつか条件が……」
生放送の特番当日。私はテレビ局の中にいた。収録スタジオでは、お涙頂戴の再会が何組も繰り広げられている。
私の出番は、番組のトリだった。緊張して生放送の光景を見守っていると、佐藤が隣にやってきていた。
「これで視聴率が取れなかったら、どうしよう」
返事をしなかった。それは私のせいじゃない。承諾したのは彼自身である。
私がテレビに出る条件は、ふたつ。
過去にマリエが取った行動を、脚色せずに伝えること。それから、実母を探しだし、この収録に連れてくること。
残念ながら後者は叶わなかった。時間もなかったし、仕方ない。死んでいるのかもしれない。そういえば、あの頃から酒浸りだった。
「続いては、タレントの青海マリエさんです。マリエさん、どうぞ」
司会者に促され、マリエが前に進み出る。すでにハンカチで目元を押さえている。化粧が全然落ちていないから、嘘泣きだった。
「はい……私は、皆さんにお伝えしなければならないことがあります」
生き別れた娘がいることを公表し、今日ここで再会するのだと話し始めた彼女の姿を、裏で冷めた目で眺めていた。
台本通りのインタビューを経て、再現VTRへ。進行は順調で、マリエは薄ら笑いを浮かべていた。自分が思っているものと、まるで違う映像が流れることも知らずに。
動画は、佐藤がマリエから聞きかじった内容と私の証言を元にして作った。事実とは一部違うのかもしれないが、もともと予定されていたものよりは、真実に近い。
なにより、彼女が先ほど言っていた「引き裂かれた恋人同士、彼の子どもが私のお腹の中に……自分で育てたかったけれど、当時のマネージャーに取り上げられて」というストーリーよりも、自己満足のお人形を生み出すためだけに代理出産させた、という話の方が視聴者の興味をそそる。ネガティブな意味だけど。
映像が進むにつれて、
「止めて! 止めなさいよっ! 嘘! 嘘よ、嘘ばっかり!」
と、発狂したマリエの叫び声がスタジオ内に響くが、実際の放送には乗らないよう、マイクを切ってある。スタジオ戻りでアップになった彼女の顔は、ぶりっこを忘れ、歯をむき出しにした獣のようだった。メイクが落ちていて、今度こそ本当の涙を流したのだと、笑いがこみあげてくる。
司会者の困惑をよそに、私はスタジオに姿を現した。マリエは娘に向けるものとはとても思えない顔で、私を睨みつける。そう、その顔はもはや私と似ているとは言えない。カメラは私と彼女の顔を交互に画面に映し出す。
「青海マリエさん。あなたは確かに、遺伝子上は血が繋がった人間ですが、私は母とは認めません」
赤の他人に自分の子どもを産ませ、引き取りもせず、養育費も払わない。親の義務を何一つ果たしていないのに、売名のために子どもを利用する母など、私はいらない。
本当は実母にも文句を言いたかったが、いない人間に感情をぶつけることはできない。
そして客席にいる、今の母へ。彼女はむせび泣いている。娘が自分だけを母と認め、選んでくれると思っているんだろう。
けれど、違う。私は選ばないことを選ぶことにした。上坂の差し出したチョコレートを口にしなかったのと同じで、毒になるものとは距離を置く。
「如月優子さん。捨てられた私をここまで育ててくれたのは、あなたです」
お母さん、と呼びかけなかったことに、果たして彼女は気づかなかった。
「でも、それだけ。世話はしてくれたけど、親としての無償の愛はくれなかった。いつも世間体を気にして、私を本当には見てくれなかった」
「清香……?」
マイクをつけていない彼女の声は、放送には乗らない。
「私は、あなたのことも、もう母と思いたくありません」
ごめんね、と今の母については多少思った。けれど、マリエにも負けず劣らずの勢いで、「清香! あんた、今まで育ててやった恩も忘れて……!」と噛みついてくる姿を見て、最後の情も枯れた。
私は真正面からカメラに向かい合った。私は女優、女優。言い聞かせれば、はらりと涙が落ちる。マリエよりもよほど、私の方が才能があるようだ。
「視聴者の皆さん。お騒がせいたしました。公共の電波をこのような私的な理由で利用したことを、深くお詫びいたします」
私は最敬礼でお辞儀をすると、そのままスタジオを退出した。あとの騒ぎは、きっと佐藤がうまくやる。結局のところ、彼もまたマリエの共犯者であり、私は許さない。
『そちらはどうですか?』
引っ越し先のマンションでのんびりしているところに佐藤が電話をかけてきたので、適当に返事をした。
佐藤はいかに後始末が大変だったかを語った。
当時、代理出産という闇医療に手を出したマリエは、警察に事情聴取を受けた。もう過去の話なので、逮捕されることはなかったが、イメージダウンは著しく、芸能界を引退せざるをえなかった。
実母を探そうとするSNSの動きもあったが、結局見つかっていない。もう死んだものと思うことにする。
育ての母に関しては、私を叩く声も大きかった。特に、母のことを知っている人たちからは、面と向かって罵倒された。何を言われても、もはやどうでもよかった。私の立場になければ、わからないことばかりなのだ。
佐藤は上の人間からかなりきつく責められたようだが、それでも視聴率至上主義なテレビ局は、彼の昇進を決めたらしい。文句を言いつつも嬉しそうにしている彼は、電話の本当の要件を、ようやく話し始めた。
『それで、如月さん。もしよかったら、あなたの父親を……』
父の名を、マリエは結局明かさなかった。たぶん、実父も芸能人なんだろう。追い詰められて暴露するかと思いきや、本当に彼らの間には、愛があったのか、彼女は口を頑として割らなかった。
もしかしたら、たんまりと口止め料や手切れ金をもらっていて、口外すれば違約金が発生する、なんて事情なのかもしれないが。
うん、そっちの方が納得できる。
私は佐藤の誘いに、きっぱりと「お断りします」と告げた。
「ひとりになって、ようやく息ができるようになったんで。もう、誰かと家族になろうなんてこと、考えていないんです」
なおも食い下がる佐藤の電話を一方的に切った。せっかく気分がよかったのに、台無しである。
「如月。アイス食べる?」
引っ越し先には、上坂が頻繁に遊びに来る。番組はリアルタイムでは見ていなかったけれど、ワイドショーや転載された動画を見て、励ましの連絡をくれた。野次馬ばかりの中で、彼のことだけは信じられた。
直接何をしてくれるわけじゃないけれど、食べ物を買ってやってきて、私に分けてくれる。いらないと言えば、冷蔵庫にしまって「いつでも食べなよ」と言う。
そういう人となら、また家族になってもいいのかもしれないな、とぼんやり思った。
「なに?」
含み笑いをする私に、上坂はガリガリくんを食べて痛んだ頭を押さえながら、問うてくる。
「なんでもないよ」
彼から受け取ったソーダ味のアイスは、これから待つ苦難を乗り越えていく軽やかさをくれる気がした。

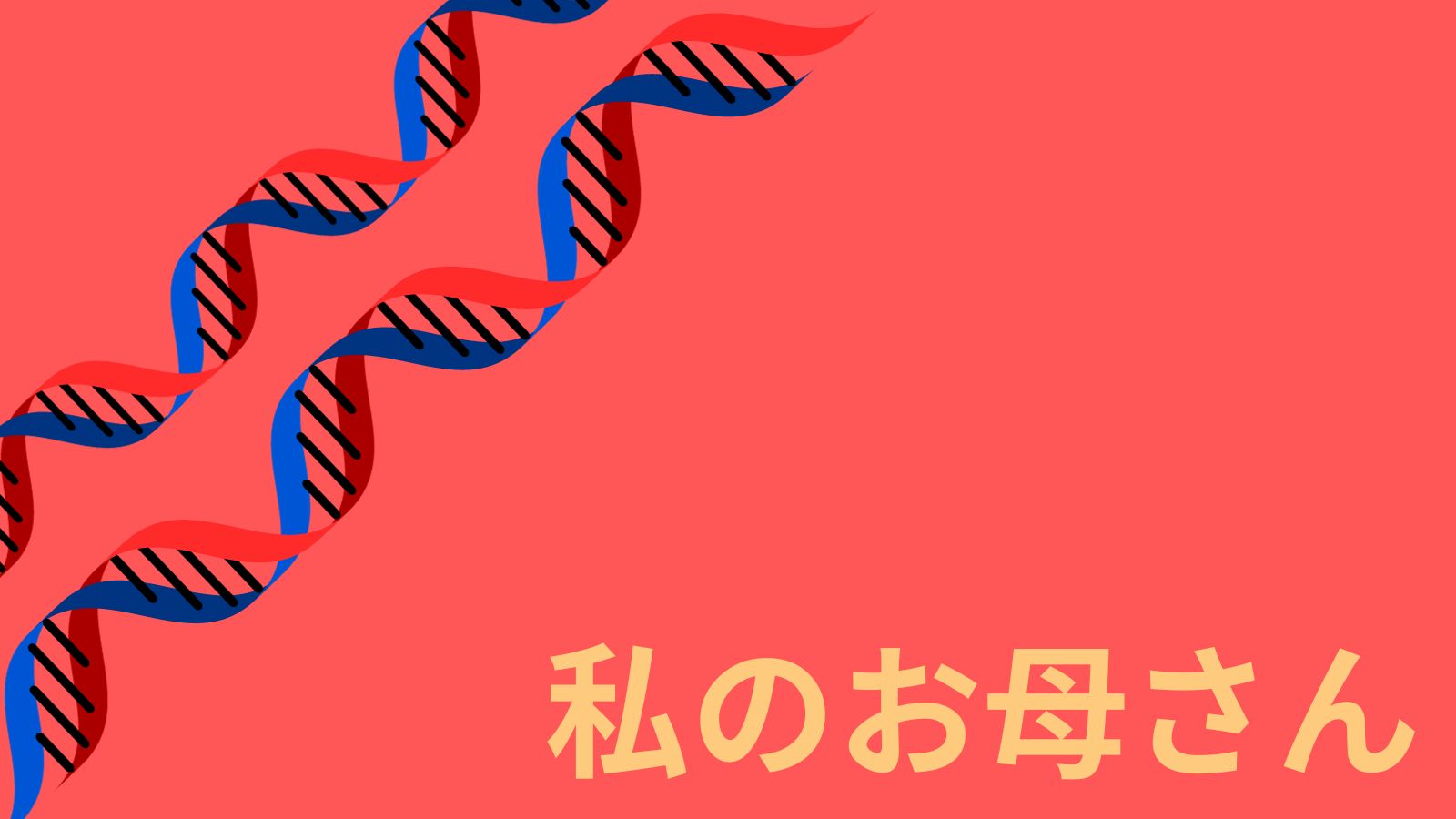

コメント