冬の寒さは、人から口数を奪う。だから、北の人間ほど、無口になるんじゃなかったか。
函館空港に降り立った俺の周りには、浮かれた連中しかいなかった。
雪を見て、はしゃいでいる子ども、追う父親。母親は赤ん坊をあやしながら、スーツケースにもたれ、片手でスマホを弄るという器用さを発揮している。
大学生くらいの女は、帰省だろうか。「ん」と差し出された父の手に、無言で荷物を手渡した。先を行く父の背に、笑みを噛みしめている表情を浮かべてついていく。
ひとりで空港に降り立ったスーツの男は、仕事で訪れたのだろう。時計を気にしつつ、タクシー乗り場へ颯爽と向かっていった。
到着ロビーで、ひとりで立ち尽くしているのは、俺だけ。
どすん、と背中からぶつかられたけれど、当の本人は涼しい顔で、隣にいる彼女とのお喋りに夢中になっている。謝罪のひとつも、ありはしない。
本当なら、俺だって。
ぼんやりと見送る視線に、女の方が気がついた。気持ち悪、と男の袖を引き、足早に去る。
別にやましい気持ちで見ていたわけじゃないのに。
最低気温のことばかり気にしていて、室内の温度のことを忘れていた。ヒートテックによる完全防御は、飛行機の中は、「まだ東京だから」と我慢できたけれど、函館に着いた途端、耐えられなくなった。
北海道なのに、なんでこんなに暖かいんだよ。
ダウンコートの中に着ていたインナーダウン、それからカーディガンも脱いで、荷物の中へ。手間取っているうちに、ロビーは閑散としていた。
ソファに腰を下ろして、深く溜息をつく。
自棄にならないで、キャンセルすればよかった。
地方空港らしく、次の便はまだまだ先。出迎え客は、ほとんどいない。寂しい空の玄関口で、俺は激しい後悔に襲われている。
宿は取ってあるけれど、他はどこへ行けばいい?
もともと、函館旅行は、彼女が「いつか絶対行く!」と言い張っていた。
照美、といういささか古風な名づけをした彼女の両親は、ふたりともGLAYの大ファン。子守歌代わりに『However』を聴いて育った彼女もまた、GLAYを熱狂的に推すようになったのは必然だった
「うちのお兄ちゃん、長男なのに次郎だから、いつも『お兄さんいますか?』って聞かれるんだよね」
というのが、彼女の鉄板の持ちネタだった。
いつかふたりで行きたいね、と、冬の大ヒット曲のワンフレーズ同様、雪が積もる頃に函館旅行を……カラオケボックスで映像を流しながら、「来年こそは」と、ガイドブック越しに顔を突き合わせていた。
その「来年」が今、このときやってきたというのに、なんで俺はひとりなんだ。
再びの大きな溜息は、二重唱になった。驚いて見れば、隣に座っている男がうなだれている。
スーツ姿だが、仕事で訪れたビジネスマンという印象はない。飛行機で多少は仕方ないとはいえ、こんなヨレヨレの状態で営業先に向かうのは、ありえない。
男は俺の視線には一切気づかず、再び溜息で自分を奮い立たせると、立ち上がった。けれど、ダメだった。
「大丈夫ですか!?」
倒れ込んだ男の顔は真っ青で、俺はすぐに駆け寄った。
救護室に運び込まれた男は、ベッドの上で眠っている。呼吸は規則正しく、「病院はいやだ」と寝言を言うものだから、空港職員もお手上げであった。
俺は、眠っている彼の顔をじっと見ていた。 職員に、「お連れ様ですか?」と聞かれ、違うと言い切ることができずに、かすかに頷いてしまった。目の前で倒れられて、見捨てることができない俺は、なんというお人好し。
『隆之は、優しいよね』
照美はいつも、そう言った。同じ微笑みが、いつしか感心から困惑に変わっていった。言外に滲ませる意味の方が大きくなったのは、どのタイミングだっただろう。
貯金が目標金額に達して、朝食ビュッフェが有名なホテルのいい部屋が取れた。ウキウキで彼女を呼び出したあの日も、同じことを言われたのだ。
『隆之は優しいよね。私だけじゃない。誰に対しても』
疲れ切った顔の照美は、スマホの画面を見せてきた。俺の腕に絡みつく、彼女とは違う女。この春入社してきた新人だ。
よく見ろよ。俺の顔、別にデレデレしてないだろ? カメラ目線でもないし、隠し撮りの嫌がらせじゃん。タイミングが悪かっただけ。そりゃ、彼女が相談があるって言うから、帰りが遅くなったり、デートをキャンセルしたりもあったけど……。いや、女だからじゃないよ? こいつが男だったとしても、新人でいろいろ心細いのはわかるし、俺も後輩から頼られれば嬉しいし……。
能面をかぶった照美を見て、言い訳の語尾は萎んでいった。無言でじっとこちらを見つめていた彼女は、不意に笑った。あ、諦めたんだ。はっきりわかった。
別れましょう、という明確な縁切りのセリフはなかったけれど、もう十分だった。
『隆之は、お人好しだね』
彼女が残した最後の言葉を、俺は男の寝顔を見ながら、思い出していた。
「ん……うう?」
唸り声に一瞬遅れて、彼の目が開いた。
おそらく、ここまでの行動を照らし合わせて、今どうなっているのか考えているのだろう。
微妙に焦点の合わない目で、見知らぬ天井を見上げている。
「大丈夫ですか?」
声をかけた。俺もまた、見知らぬ人間。あまり刺激を与えたくない。
ゆっくりとこちらを向いた男と、しっかり目を合わせて、「隣で倒れられたもので」と、通りすがりの者だと主張する。
彼は慌てて起き上がった。
「す、すいません。大変ご迷惑を……」
あまりの恐縮っぷりに、ベッドで土下座でも始めるのではないかと思った。落ち着くように説得すると、男は深呼吸を始める。
どうにか冷静になった彼に、
「誰か迎えは?」
と尋ねれば、首を横に振る。
「お仕事ですか?」
違うだろうなあ。
思いつつ、無難な質問を投げかけると、ただでさえ白い顔が、さらに紙のようになる。
「……お恥ずかしながら、クビになりまして。いや、実際は、自主退職なんですけど」
ブラック企業勤めだった男は、忙しさとパワハラによって、鬱を発症。休職は認められず、限界になったところで退職勧告がなされ、今に至る、と。
比較的ホワイトな職場であっても、「あ~、仕事やめてぇなあ」と思うことは多い。ブラックならなおのことだろう。
ギリギリアウトのラインまで追い詰めて、壊れたらポイ捨て。人権もなにもあったもんじゃないのに、彼は「自分が悪い」と思い詰めていた。
「大学も東京に出してもらって、就職して、期待されてたんですよね、正直。なのに挫折したから、ちょっと親に顔合わせづらいなって思ってたら、こんなことに……あ、鬱はもう治っているんですけどね」
そう言って力なく、わざとらしく声を上げて笑った男の病は、とうてい治っているとは思えなかった。
ここで別れたら、明日の朝には、海から彼の死体が上がってしまいそうな。
その想像があまりにもリアルだった。青白い彼の顔は、死体と変わらない。
俺は思わず、提案していた。
「そしたら、俺と一緒にホテルに泊まってくれません? 連れにドタキャンされまして」
ああ、本当にお人好し。
名前も知らない男と、ダブルベッドの部屋に寝る今夜のことを思うと、憂鬱になったけれど、顔には決して出さなかった。
遠慮する男を無理矢理バスに乗せて、駅前のホテルへ向かう。チェックインの時間にはまだ早いが、連れの体調がよくないことを電話連絡すると、こころよく受け入れてくれた。
ロビーのソファに座らされた男――佐藤は、落ち着かない様子で、キョロキョロしていた。
「こ、こんなきれいなホテル、入ったことないです……!」
「奮発したんですよ」
なにせ、念願の函館旅行だったから。プロポーズの予定はなかったが、勢いで申し込む可能性はあった。
個人的な事情は、佐藤には言わなかった。彼は「気にしい」な性質なのは、この短い間でもわかった。会社でも、余計なことに気を回し過ぎた結果、鬱になったにちがいない。
スイートルームやプレミアムルームがあるのは、十三階。スタッフが俺たちの荷物を運び、エレベーターから先導してくれた。
フロントの女性といい、ボーイの男性といい、さすがにプロである。男ふたりでキングサイズのベッドひとつしかない部屋に泊まろうとしているのを、奇異の目で見たりせず、丁寧な接客をしてくれるのだから。
「それでは、何かございましたらフロントまでお願いします。よい旅を」
深く一礼をして出て行ったのを見送り、俺は室内を見回した。
1Kの俺の住むアパートよりも、はるかに広い。薄給とまでは言わないが、旅費のために切り詰めた生活をしていたから、住まいもまぁ、それなりだ。
壁際に鎮座した巨大なサイズのベッドのことは一度忘れる。幸いソファがあるので、俺はそちらで寝よう。
さすがに夜景を売りにした街のホテルとあって、窓が大きい。佐藤は窓際に近づいていって、眼下の町並みを見下ろしていた。
落ちくぼんだ目には、疲れと諦めが見える。郷愁というよりも、恐れが浮かんでいる。もしもこの窓が大きく開くのだとしたら、うつろなままで飛び込んでいってしまいそうな、危うさがある。
一呼吸整えて、「ベッド、使ってください」と促した。佐藤は振り返り、首を横に振る。
「悪いですから」
「いやいや、気にしないでください。倒れたばっかりなんですから、一回横になって」
何度かそのやりとりを繰り返すうちに、佐藤の顔に血色がようやく戻ってきた。顔を見合わせて笑い、
「元気になったなら、外出ます?」
と、誘ってみた。
そういえば、昼もまともに食べていないし。思い出したら、腹が催促してきた。
佐藤は、腹の虫に向かって頷いた。
照美がいたなら、「ここが行きつけなの!」などと、聖地巡礼的なことをしたがっただろう。
だが、俺は正直、GLAYのことは嫌いじゃない止まりなのだ。そもそも世代ど真ん中じゃない。
カラオケに行けば、「この歌低くて歌えない」という照美にリクエストされて、そのために覚えただけなのだ。
だから、美味ければどこでもよかった。こだわりは一切ない。照美のためにガイドブックを買い込んではいたが、一度読んだきりで、持ってこなかった。
スマホで調べられるし、それに。
「佐藤さん、美味い店知らないっすか?」
地元民は、ガイドブックに載らない隠れた名店を知っているはず。そんな期待を込めて尋ねたが、気の毒なくらい眉を下げた佐藤は、
「あの、僕、高校卒業してからあんまりこっちに帰省する暇もなくて……」
と、自分のスマホであれこれいじり始める。その指は、微かに震えていた。余計なプレッシャーを与えてしまった。
「ああ、大丈夫大丈夫。ラーメン屋なら、テキトーに入ったって美味しいでしょ、たぶん」
彼の背中を押して入った店。昼時をはずしているからか、人が少ない。
カウンターとテーブル席がたったふたつしかない小さな店だ。観光地なのにこんなに暇で、大丈夫か?
そんな気持ちはおくびにも出さず、カウンター席に座った俺は、メニューを開いた。
やっぱり函館といったら塩だろうな。それから、餃子も美味そう。
ちらりと伺うと、佐藤はメニューを眺めていた。ラーメンだぞ? そんなに悩むことあるか?
「もう呼んでいい?」
一応、一声かけた。佐藤は視線をうろうろさせて、小さく頷いた。
「すいませーん」
威勢のいい店員に注文し、佐藤を促す。彼はメニューで顔を隠しながら、「同じもので」と、蚊の鳴くような早口で注文した。
すぐに同じ店員が餃子を持ってくる。一皿六個。大きめで、見ただけでわかるジューシーさ。酢醤油をつけて、まず一個。予想通りの肉肉しさ、そして皮のもちもち感に、舌鼓をうつ。
ビールも頼むべきだったな。
そう思いながら、餃子を立て続けに三つ食べたところで、ラーメンが運ばれてきた。透き通った黄金のスープに、縮れ麺。具材はシンプルすぎるくらいで、餃子のたっぷり餡とは真逆だった。
ずるずると麺を啜る。普段は豚骨! 背脂! いろいろマシマシ! みたいなラーメンを食べに行くことが多い。あっさり塩味は新鮮で、いくらでも食べられそうだ。
ふと、隣に座る佐藤を見れば、あまり食が進んでいない。ラーメンをのびないうちに食べるのに精一杯で、餃子には一切手をつけていない。
「それ、全部食えます?」
自分の分をすべて平らげて、佐藤に声をかける。彼の顔は、倒れたときとはまた違う青みを帯びている。麺を口いっぱいに頬張り、目にはうっすら涙が浮かんでいた。
ためらいがちに、ゆっくり小さく横に振られた首に、俺は「手伝います」と、餃子の皿を引き受けた。
食べられないなら、餃子なんて頼まなきゃいいのに。ラーメンだって、塩じゃなくて、本当は他の味がよかったのかもしれない。少なめにするとかさ。
少し冷めた餃子を咀嚼しつつ、佐藤がだらだらとラーメンを食べているのを眺める。
そういえば、照美とのデートのときも、似たようなことがあった。
居酒屋で、最初はテンション高く、「何にしよー」とメニューをめくっていた照美が、俺が注文した料理が運ばれてくるのを見る度に、なんだか悲しそうな目に変わっていった。
そのときは、「別に気にせずに好きなの頼めば」と言った。けれど、彼女は首を横に振り、俺が頼んだフライドポテトや唐揚げを突いていた。
腹が減ってるんだから、さっさと注文した方がいいに決まっている。よかれと思ってやっていた。
「すいません。僕、食べるの遅くて」
「いや、俺がせっかちなだけだから」
せっかち。そうだ。照美は「お人好し」の他に、「せっかち」と俺のことを何度も諫めた。その度に、「お前がとろいだけだよ」と、冗談めかしていた。「ごめん」の一言くらい、言ったっけ? 記憶がない。
「川添さん?」
店を出て、ふるりと身を震わせた佐藤に呼ばれ、俺は我に返った。
今日だって、佐藤にちゃんと確認すればよかったのだ。「もう呼んでいい?」じゃなくて、もっと他の言葉をかけるべきだった。
食事をするのが苦痛になる相手と、よい人間関係を築けるはずがない。
照美と俺は、仲のいい恋人同士だったと思う。大学一年から付き合って、社会人になってからも続いていたのだから。周りはみんな、俺たちが結婚すると思っていた。からかわれたことも、何度もある。
俺だって、いつかは……って、そう思っていた。
だけど、笑顔の裏で照美は、俺の嫌なところ、許せないところを少しずつ積み重ねていって、愛情が冷めたのだ。
今さらながら、別れが胸に迫ってくる。
俺はラーメンに入れたコショウのせいだとごまかして、下手なくしゃみの真似をした。
函館は、何もないところですよ。
佐藤の言葉に、俺は「いやいや」と、否定の合いの手を入れた。
「何にもないことはないでしょ。食いもんは美味いし」
実際、ラーメンは美味かった。
佐藤は俺のフォローに、うっそりと笑った。
「駅前のシャッター、見たでしょう?」
函館駅周辺で活気があるのは、土産物屋や飲食店くらいのものだった。市民が日常的に利用するような商店は、シャッターを下ろしているところが多かった。
「僕が子どもの頃から、ここは変わりませんよ」
遠い目をする彼は、街の風景に自分自身を重ねているようだった。地元に帰ってきたところで、働こうとしても、仕事がない。すでに次の不安に支配されて、佐藤はやっぱり、このままだとどこからか飛び降りてしまいそうだ。
「そ、そうだ。俺、暗くなる前に行ってみたいところがあったんだよね」
ホテルは一泊二日、飛行機は明日の夕方に羽田行きを予約してある。滅多に来られる場所ではないから、行ける範囲で観光したい。だが、正直な話、五稜郭と函館山くらいしか知らない。
「どこですか? 僕で案内できるところであれば行きますけど」
函館山は、暗くなってから行くのがセオリーだから、ここは無難に五稜郭か。いや、でも。
ふと思い出したのは、照美の顔。
絶対に函館に行くんだ、と、ガイドブックを見つめていた横顔。
もしも隣にいるのが佐藤じゃなくて照美だったら、きっと彼女は。
「……本当に何にもないですよ」
呆れつつも、佐藤が連れてきてくれたのは、緑の島だ。東京にも夢の島っていうのがある。埋め立て地にはなぜか、きれいな名前をつけたがるのが人情というものなのか
「何もないっていうか」
見渡す限り、雪だった。純白というイメージだが、俺たちの前にそびえ立つ(そう、そびえ立っているのだ!)雪山は、白というよりも灰色、ところどころ黒だった。
「今年は雪が多いみたいですね。僕がいた頃も、こんなに積もってるのは見たことないです」
市内の除雪車が最終的に雪を捨てる場所。緑の島は、灰の島。
雪のない時期は、広場でイベントをやったり、スポーツを楽しんだりできるそうだが、本当に何にもない。管理事務所やトイレ、水飲み場や自販機はあるが、だだっ広い人工島だ。
ここは以前、GLAYが野外ライブを行った聖地である。熱狂的ファンである照美の家族だが、さすがに全員分のチケット+航空券+宿泊費用を考えた末に、泣く泣く諦めたという話を、何度も聞いた。
俺は雪山を見上げながら、夏の青空を想像する。
北海道、夏は暑くても爽やかだろう。突き抜けた夏空に、響き渡る音楽と歓声。
ライブの映像は、照美と一緒に見た。カラオケのパーティールームをわざわざ借りて、タオルをぶんぶん振り回したことを、今でも昨日のことのように思い出せるのに。
照美は俺の隣にいない。
冬の函館で、俺の横で白い息を吐き出しているのは、今日知り合ったばかりの男だ。
「地元でも、うちはこっちの方じゃないから、あんまり来たことないんですよね……川添さんは、どうして?」
「え?」
物思いに耽っていた俺を、佐藤は正気に引き戻した。怪訝な顔をして俺の顔を見つめてくる彼の頬は、寒さで赤くなっている。
今日が初対面なのに、いろんな色を見ているな、と思うとおかしくて、旅の恥はなんとやら、と、俺はこの旅行について話をした。
「本当は、彼女と一緒に来る予定だったんだけど、振られて」
佐藤は微妙に引きつったが、驚きはしなかった。まぁ、キングサイズのベッドが鎮座している部屋なんて、恋人以外と利用することはない。
「その彼女がさ、GLAYが好きで。ずっと、函館旅行に行こう! って言ってたから、頑張って金貯めてたんだけどさ」
吹きさらしの島でふたり、ぼーっと暮れていく空を眺めている。照美と一緒に訪れていたら、雪山しかない広場であっても、テンション高く写真を撮りまくっていたに違いない。
『あたしも、ここで叫びたかったな~!』
なんて、幻聴すら聞こえてくるようだ。
「なんで振られたんだろうな」
本当は、もうわかっている。俺の、外にはいい顔をして親切にしながらも、身内に対しては自分の都合を優先させる態度に、愛想が尽きたのだ、と。
それでも俺は、照美への少しの恨み節を載せて、「どうして」と、疑問を口にした。こんなこと、聞かされる佐藤の身になってみろっていうのに。
佐藤は黙っていたかと思うと、急に俺の手を取った。
「佐藤さん?」
「川添さん、いきましょう。そろそろここ、閉まりますし」
出会って初めて、佐藤の方が俺を引っ張った。されるがままについていく。名残惜しく振り返る緑の島はやっぱり、その名前がふさわしくないほど、悲しいくらい灰色だった。
佐藤によって、ロープウェイに乗せられた。標高三三四メートルしかない山の頂上には、カップラーメンの待ち時間と同じくらいでたどり着いてしまう。
冬は日が落ちるのが早く、街の灯が灯り始めるのも早い。山頂は麓よりも寒く、俺はホテルに置いてきてしまった防寒具の類いを恋しく思いつつ、くしゃみをした。
テレビや写真で見たことのある光景が、眼下に広がっている。
両サイドに広がる海は、静寂の黒。吸い込まれていきそうな闇とは対照的に、市街地の灯りは、温かく地上を照らしている。
正直、この目で見るまではあんまり期待していなかった。函館の人口は、中核都市にも届かない。百万人都市の札幌の方が、今じゃ新・三大夜景と絶賛される始末だ。
けれど、実際に見てみると、やっぱり味わい深く、感動的だ。写真を撮っている観光客の歓声なんて、耳に入ってこないくらい、俺はなぜかわからないけれど、引き込まれていた。
ああ、照美と一緒に見たかったな。
ちょんちょん、と袖の辺りを突かれて、振り返った。佐藤が遠慮がちに、ティッシュを差し出していて、俺は頬が濡れて、今にも凍ってしまいそうに――いや、これは大げさだな――なっていることに気づく。
受け取ったティッシュで涙を拭いていると、なぜか佐藤も泣いていた。
「なんで」
「なんででしょうね。でも、この夜景見てたら、なんだかわからないけれど、泣けてきたんですよ。川添さんも、そうでしょう?」
結婚をうっすら考えていた、長い付き合いの彼女に振られても、俺は理不尽に怒ったり、悲しんだりすることがあまりなかった。そりゃ、自棄になって北海道くんだりまで来たけれど、それだって半分くらいは、せっかく貯めた金がもったいないとか、そういう理由だったように思う。
今初めて、振られて悲しいとか悔しいとか、そういう感情が爆発している。たぶんそれは、佐藤も同じだろう。涙を流すことは、エネルギーのいることだから。
「佐藤さんさ、函館には何もないって、言ったじゃん」
「はい」
「でもさ、あるよ。この景色があるんだよ、この街には」
「そう……ですね」
この山からの眺望は、人の心を動かすきらめきだ。佐藤が微笑んでいる。それは、これまでとは明らかに違う、心からの笑顔だ。もう、彼は大丈夫だろうと感じた。
「なあ、歌おう!?」
「はっ? 歌!?」
彼女が一番愛した、冬の歌。そして再び函館に再訪することを誓って、俺は最初のハミングから歌い始める。
周囲の奇異の視線を気にして、最初は戸惑っていた佐藤も、原曲はバラードなのに、調子っぱずれにしか歌えない俺を見て笑い、一緒に歌ってくれた。
いつかふたりで。いいや、ひとりでだって。
肩を組んだ俺たちの横を、「何アレ」と、通り過ぎていく人々をよそに、泣きながら、笑いながら、どつき合いながら、俺たちは一曲を歌い上げた。
夜景を構成する家の灯りは、ライブ会場のペンライトと違って、揺れたりはしない。けれどきっと、ステージから見る客席よりも、ずっとずっと、明るいにちがいない。
今日のこの経験が、生きてく強さの糧になる。
白い息を吐き、そして大きく吸い込んではまた、大声をあげた。

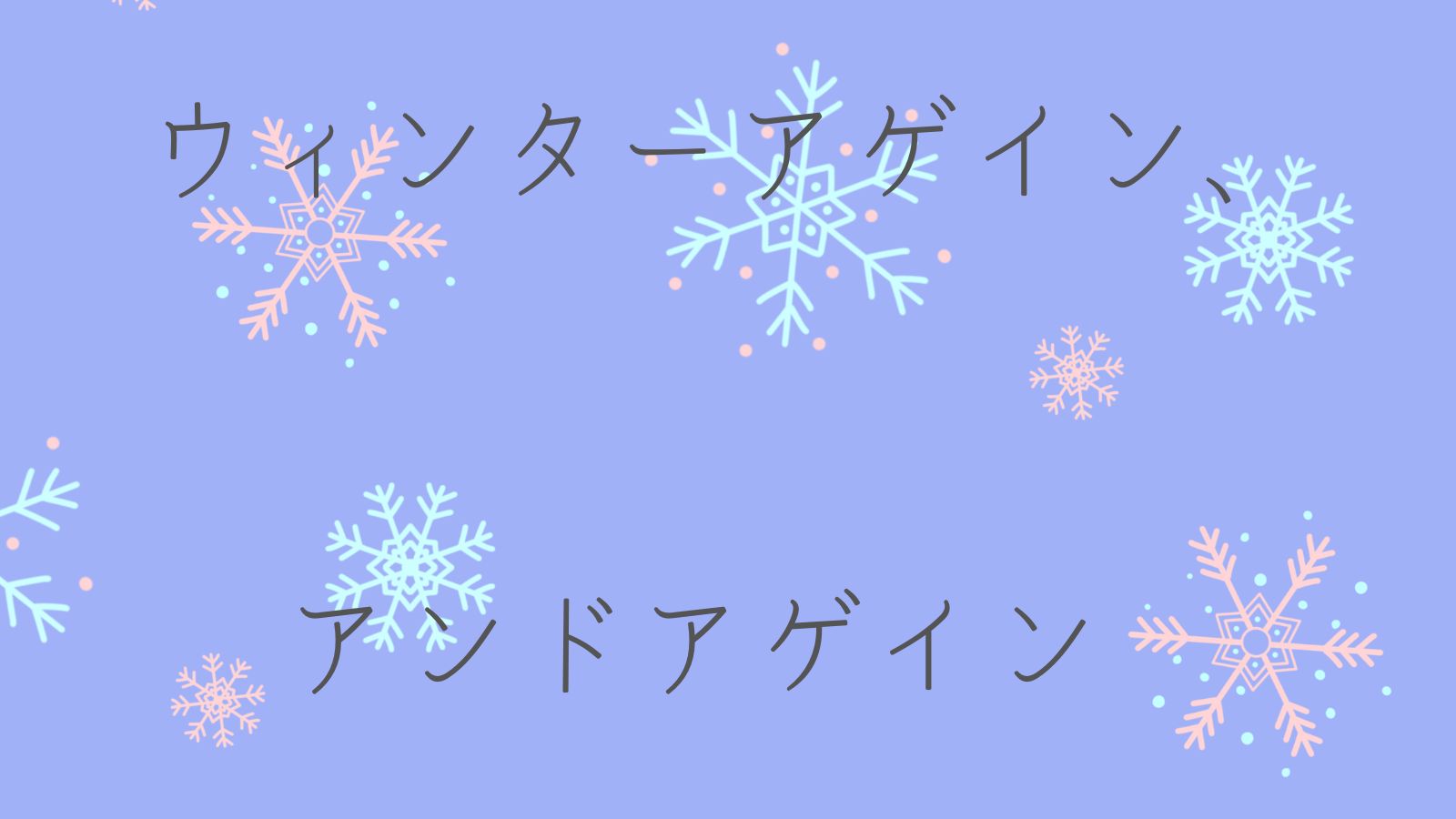


コメント